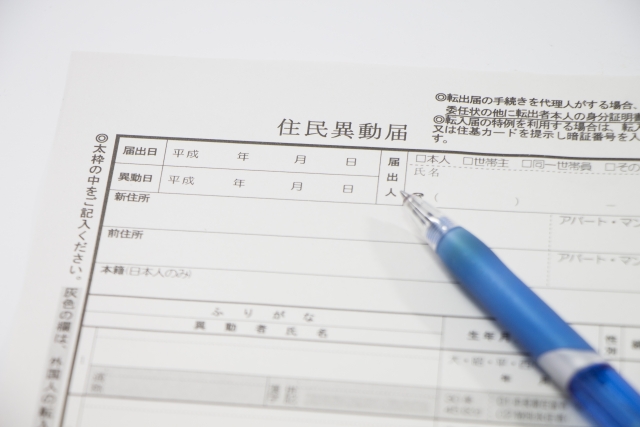敬語はビジネスシーンや日常での良好なコミュニケーションに欠かせないスキルです。
しかし、正しいと思って使っている敬語が実際には誤解を招いたり、相手に失礼と取られたりすることもあります。
「知らずに使っている言葉が、実は相手に悪印象を与えていた」という経験はありませんか?
今回は、敬語の使い方に潜む落とし穴を詳しく解説し、特に誤用されやすい10のフレーズを取り上げます。それぞれのフレーズに対する正しい使い方や改善策も解説しつつ、最後には敬語を適切に活用するためのポイントをご紹介します。
正しい敬語を身に付けて、信頼されるコミュニケーションスキルを習得しましょう。

敬語の使い方に潜む落とし穴とは
正しく敬語を使っているつもりでも、時には逆効果になってしまう場合があります。
敬語は「相手に敬意を示す言葉遣い」という基本的な概念に基づいていますが、これが必ずしも相手に良い印象を与えるものとは限りません。なぜでしょうか?
敬語が引き起こす誤解の原因
敬語が相手との適切な距離感を保つために役立つ一方で、「間違った使い方」や「過剰な表現」で誤解を生じさせたり、不快感を与えることがあります。敬語が誤解を生む原因の一つは、「形式だけを整えて内容が伴わない」ことです。例えば、無理に丁寧すぎる言葉を使ったり、適切でない場面で敬語を使ったりすると、かえって軽視されやすくなります。特に、二重敬語や過剰なへりくだりは、相手を混乱させる原因となることがあります。
また、言葉の使い方次第では「不自然」「機械的だ」と取られる可能性もあります。特に、ビジネスシーンでは敬語の正確性が相手の信頼度や自分の評価に直結します。
無意識に信頼を失う理由
敬語は正しく使えば信頼を深めるツールになりますが、少しでも間違えると「自信のなさ」や「注意不足」として相手に見られてしまいます。特に以下のような点が信頼を損なう要素となります。
1.二重敬語や過剰表現:
相手に違和感を与え、不快感を生じさせる。
2.非丁寧な表現:
気軽な表現が誤解され、失礼に映る。
3.言い回しの曖昧さ:
意図を理解し難く、誠意が感じられない。
知らずに使ってしまう信頼を損なう10のフレーズ
何気なく使いがちな敬語の中には、実は間違っているものや適切でないものがあります。ここでは、特に注意が必要なフレーズを10個挙げ、さらにその正しい使い方を示します。
1. 「おっしゃられる」などの二重敬語
「おっしゃられる」という言い方は、敬語を重ねてしまった二重敬語の典型です。
正解:「おっしゃいます」「おっしゃっていました」を用いましょう。
例)
✖️「社長がおっしゃられていました」
✔️「社長がおっしゃっていました」
2. 「了解しました」は丁寧ではない?
「了解しました」という表現は一見問題ないように感じますが、目上の人には不適切です。
正解:「よろしいでしょうか?」「承知しました」や「かしこまりました」を使いましょう。
例)
✖️「了解しました。すぐに対応します」
✔️「承知しました。すぐに対応いたします」
3. 「よろしかったでしょうか?」の誤用
過去形の「よろしかったでしょうか」は丁寧さを表現しようとして逆に不自然です。
正解:「よろしいでしょうか?」が正しい選択です。
例)
✖️「資料の内容はこれでよろしかったでしょうか?」
✔️「資料の内容はこれでよろしいでしょうか?」
4. 「お疲れ様です」の誤用例
「お疲れ様です」は便利な表現ですが、相手によっては使い方を誤ると失礼に取られることがあります。
正解:改まった場では「お世話になっております」を選ぶほうが無難です。
5. 「そのようですね」の曖昧さ
「そのようですね」は適当に同意している印象を与えることがあります。
正解:具体的に「確かに〜ですね」とすることで誠実さを表します。
6.「お聞きになられましたか?」二重敬語
「お聞きになられましたか?」では二重敬語が用いられています。
正解:「お聞きになりましたか?」が簡潔で正しい表現です。
7. 「〜していただければ幸いです」の多用
繰り返し使用すると、形式的すぎて相手に冷たい印象を与える恐れがあります。
正解:柔らかく感じさせるには、「〜で助かります」を使ったり、簡潔に伝えましょう。
8. 相手を指す表現:役職の敬称に注意
「社長様」「部長様」のような表現は不適切です。役職に敬称を重ねないよう、「社長」「部長」と丁寧な口調や言い回しを用いましょう。
正解:役職名は単独で使い、「社長」「部長」で十分です。
例)
✖️「社長様にお伝えします」
✔️「社長にお伝えします」
9. 「〜させていただきます」の過剰使用
「させていただきます」は丁寧さが感じられる印象がありますが、過剰に乱用すると聞き手にしつこく感じられることがあります。
正解:シンプルに「いたします」で表現する場面も検討しましょう。
例)
✖️「確認させていただき、ご連絡させていただきます」
✔️「確認のうえ、ご連絡させていただきます」
10. 過度のへりくだりは逆効果
相手へ必要以上にへりくだった遠慮しすぎた言葉遣い(例:誠に恐縮ですが〜)は、時に不自然さを招きます。
正解:状況に応じた適切な敬語を使用し、スマートな言い回しを選ぶようにしましょう。
正しい敬語を使って信頼を築くために
敬語は相手の立場を尊重し、自分の印象を良くするための強力なツールです。しかし、敬語が相手に好感を与えるどころか、誤解を生んで信頼を損なってしまうケースもしばしばあります。それを防ぐためには、正しい敬語の使い方をしっかりと理解し、日々の会話の中に取り入れる努力が必要です。誤解を避け、信頼される言葉遣いを目指すためにはどうすれば良いのでしょうか?
1.適切なフレーズの選び方
言葉遣いの正確さや適切さは、敬語を使う上での基本です。どんな場面でも同じ敬語表現を使うのではなく、状況や相手に応じて丁寧な表現を選びましょう。日常生活やビジネスシーンでよく使われる表現には、いくつものパターンがあり、場に応じた適切な敬語を知っておくことが重要です。
具体例を覚えるポイント:
毎回同じ表現を使うのではなく、どの程度丁寧な表現を求められる場面なのかを考慮して、フレーズを選ぶ習慣をつけましょう。また、「ありがとう」と言いたいときに感謝の言葉をさらに多彩な表現に置き換える練習をすることで、場面ごとに自然な言葉を使えるようになります。
2.言葉遣いに磨きをかけるための練習法
正しい敬語を身に付けるためには、知識として得るだけでなく、実際に慣れるまで繰り返し練習することが必要です。耳で聞く敬語教材や、信頼のおけるビジネス書を参照し、正しい言い回しを体系的に学ぶことが有効です。また、自分の話し方を録音して聞き直すことで、無意識のうちに使っている間違いを客観的に確認することができます。
仕事や日常で意識的に敬語を使う:
例えば、職場や取引先の方へのやり取りではもちろんのこと、上司やお客様だけでなく同僚や後輩にも礼儀正しい言葉を使うよう意識してみましょう。また、プライベートであっても、店員や配達員の方との会話で丁寧な敬語を取り入れるなど、小さな場面での実践が大切です。
2.継続的な改善が信頼を高める鍵
敬語は一度学べば終わるものではなく、継続的に練習と改善を繰り返していく必要があります。間違った敬語を使ったことで気づくことがあるという点で、日々の学びに意味があります。時々振り返る習慣を身につければ、あなたの敬語は自然と相手に好印象を与えるものへと進化していくでしょう。
自分の言葉遣いを振り返る:
「今日はきちんとした敬語を使えたかな?」「もっと別の言い回しがあったかも?」と、一日の終わりに振り返る習慣を持つのも効果的です。間違いや曖昧な表現を確認し、翌日以降に改善することを意識しましょう。
失敗を恐れない:
敬語を学ぶ際、多くの人が陥りやすいのが「間違うことへの恐れ」です。「もし敬語を間違ったら失礼に思われるのでは……」「変な言葉遣いになってしまったらどうしよう」と不安に感じて、結局いつもの砕けた話し方に逃げてしまう、ということはありませんか?
ですが、敬語のスキルを本当に身につけたいのであれば、失敗を全く恐れる必要はありません。むしろ、間違いをしてしまった時が最大の学びのチャンスです。失敗したことに気づき、そこから正しい使い方を学べたなら、同じミスを繰り返さなくなります。それこそが成長の証です。

敬語の基本ルールを再確認
正しい敬語を使うためには、まず敬語の基本的なルールを理解することが重要です。敬語は美しい日本語の一部であり、適切に使うことで相手への敬意や配慮を示し、信頼を築くことができます。しかし、種類や使い分けを理解していないと、無意識のうちに相手に失礼な印象を与えてしまうことも。ここでは、敬語の基本的な種類とその使い方について詳しく解説していきます。
敬語の種類をしっかり理解しよう
敬語には大きく分けて「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」という種類があります。それぞれの特徴を理解し、上手に使い分けることが、正しい敬語を習得するための第一歩です。
1. 尊敬語(相手の行動や状態を高める言葉)
尊敬語は、相手や目上の人の行動や状態を高め、敬意を表すために使われます。相手が主語となる時に用いるのがポイントです。
- 主な特徴:「お〜になる」「〜れる」「〜られる」といった表現を使うことで、相手を立てる言葉遣いになります。
- 具体例:
「言う」 → 「おっしゃる」
「する」 → 「なさる」
「行く/来る」 → 「いらっしゃる」
「食べる」 → 「召し上がる」
例文)「社長がおっしゃったとおりです。」
(「言った」ではなく「おっしゃった」を使い、社長を立てる)
尊敬語は相手を高めることで敬意を表す表現なので、自分の行動には使えません。
2. 謙譲語(自分や身内の行動をへりくだって表現する)
謙譲語は、自分や自分の関係者の行動を低く伝えることで、相手に敬意を表す言葉です。相手への配慮を込めたい時に使います。
- 主な特徴:「お〜する」「〜申し上げる」「〜いたす」といった表現を使うことが多いです。
- 具体例:
「言う」 → 「申し上げる」
「する」 → 「いたす」
「行く」 → 「参る」
「見る」 → 「拝見する」
例文)「私が参ります。」
(「行きます」ではなく「参ります」を使い、自分をへりくだる)
謙譲語では、相手に対して「自分を下げる」ことで、相手を立てる効果が生まれます。そのため、自分の行動や自分を含むグループの行動について表現する際に使用します。
2. 丁寧語(話し言葉を丁寧にする表現)
丁寧語は、文章全体を丁寧にするための表現です。話し相手に対して「です」「ます」「お」で終わらせることで、敬意を伝えるシンプルな方法です。
- 主な特徴:相手に対する特定の敬意ではありませんが、礼儀正しさを持たせるのに適しています。
- 具体例:
「言う」 → 「言います」
「する」 → 「します」
「行く」 → 「行きます」
「見る」 → 「見ます」
例文)「こちらに資料があります。」
(「ある」ではなく「あります」を使うことで、丁寧な表現になる)
丁寧語はビジネスの場面だけでなく、日常会話でも使いやすい表現として多く用いられます。
間違えやすい尊敬語と謙譲語
尊敬語と謙譲語を混同しないように注意が必要です。例として、「お客様が『伺う』」などの表現は誤り。尊敬語の「いらっしゃる」を用いるのが正しい使い方です。具体例やシンプルな表現を積み重ねて習得していきましょう。
正しい敬語が信頼を生む
敬語の使い方一つで、あなたが相手に与える印象や信頼度は劇的に変わります。「この人と仕事をしたい」「この人にお願いしたい」と思わせる力は、あなたの言葉遣いに宿っています。
❝人は言葉で人を信じ、絆を深め、未来を築く❞
例えば、ビジネスシーンでは相手の信頼を得られるかどうかが成功の鍵を握ります。そして、その信頼を築くための最も基本でありながら最も重要なスキルが、言葉遣いです。適切な敬語を駆使することで、あなたの人柄や専門性、さらには誠実さが相手に伝わり、自然と「この人なら安心だ」という評価が得られるのです。
正しい敬語を使うことは、知識やセンスを示すだけではありません。それは相手への敬意を言葉に乗せることであり、配慮や信頼を形にする行為なのです。たとえ能力が同等であっても、言葉遣いが丁寧で適切な人は、より早く、そして深く相手との信頼関係を築くことができます。
ぜひ、ここで得た知識を実践に移し、一つひとつ丁寧に言葉を届ける習慣を始めましょう。敬語の力を武器に、より円滑で質の高い対人関係やビジネスコミュニケーションを築き上げてください!